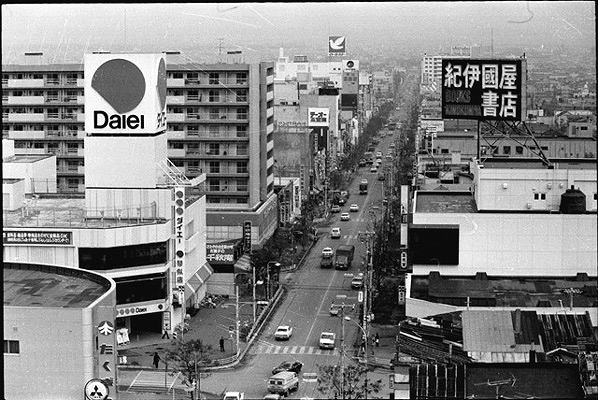間、髪を容(い)れずということがあります。 これを兵法にたとえて述べてみましょう。 (中略) 人が打ちこんできた太刀に心が止まれば、そこに隙ができます。 その隙にこちらからの働きが、お留守になるのです。 向こうが打ってきた太刀と、それに応える我が方の働きとの間に、髪の毛一本入らぬようなら、人の打つ太刀は自分の太刀となるのが当然です。 禅の問答でも、このように間髪を容れない心の状態を大切...
Read More立禅では意念(イメージ)を使うことがある。 四方の空間とバネで繋がっており、全身が空間全体と協調して動く。 全身が周囲の空間、自然とつながっているかのようだ。 敵と相対したときもその相手だけにとらわれることなく、天地と呼応する。 自己と周囲の環境との一体化ともいえるだろう。 意念を使わず、ただ立つこともある。 ただそのままに立つ。 野生動物が休息しているときのようだ。 くつろい...
Read More無明住地を、あなたがよくご存知の兵法にたとえて説明してみましょう。 敵が刀を振り上げて切りかかってきたとします。 その刀を一目みて、「あっ、来るな。」などと思うと、相手の刀の動きに心がひきずられて、こちらは自由に動くことができずに切られてしまいます。 打ちこんできた刀を見ることは見るのですが、それに対して、ここで相手の刀を切りかえそうとか、どう打ちこもうかなどと思慮分別を一切持たずに、つまり...
Read More死のうと思うな 生きようとも思うな ただ、戦え (「水滸伝」 北方謙三) 生死をかけた闘争は幸いにも経験がない。 だが、組手でも似たところがあるように思う。 強敵であればあるほど、勝つとか負けるとか、そんな先のことは考えてはいられない。 この瞬間の突きや蹴りに対応しなければならない。 ただ、一心に向き合うだけだ。 今、この瞬間にやれることを、やる。 そんな没我の瞬間がたまら...
Read More