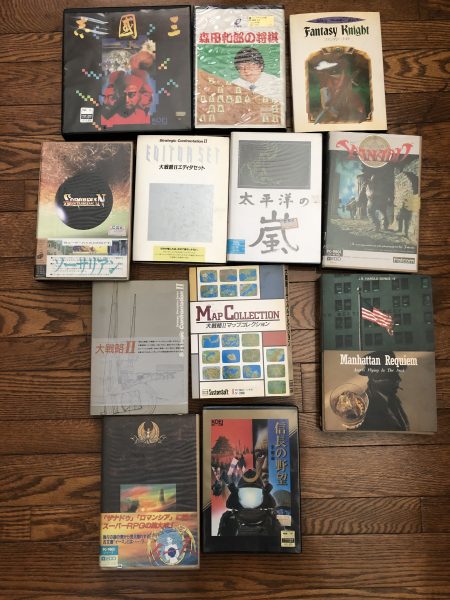死のうと思うな 生きようとも思うな ただ、戦え (「水滸伝」 北方謙三) 生死をかけた闘争は幸いにも経験がない。 だが、組手でも似たところがあるように思う。 強敵であればあるほど、勝つとか負けるとか、そんな先のことは考えてはいられない。 この瞬間の突きや蹴りに対応しなければならない。 ただ、一心に向き合うだけだ。 今、この瞬間にやれることを、やる。 そんな没我の瞬間がたまら...
Read More「学ぶ」の語源は「真似ぶ」とする説がある。 気功は自然をまね、その気を我が身に写し取る行為だ。 立禅は中国では站椿というが、これは樹木の真似であるともいう。 大樹のごとく静かに立ち、その静けさ、何事にも動じない強さを真似るのだ。 真似をすればそうなる、ある程度は。 眉間にシワを寄せていれば険しい気分になるし、笑顔をつくっているとなんとなく機嫌がよくなってくる。 姿勢を正していると心...
Read More友人からこんなメールをもらった。 ーーーーー 松井さんは、手の平と甲を交互にひらひらさせて コレ、コレ、コレ、と表現していましたが、 これは、現在過去未来が連続的ではなく、 今、という感覚が断続的な”点の連続”という感じなのでしょうか? ーーーーー それにこんな返事をした。 ーーーーー 過去現在未来の連続性がない、ということは表現として「事実」に近いものがあるかもしれません。 ...
Read More会員の松本さん。 親分肌で器の大きな人だ。 建設現場で働いておられるので、私のイメージは半纏を着た宮大工の棟梁。 以前は芦原空手をされており、組手姿もしゅっとしている。 彼から聞いた話だ。 ある日の建設現場のこと。 2階ほどの高さの足場で足元の工具を取ろうとしたら、そこに足場がなかった。 それで数メートル、落下したそうだ。 大怪我レベルの事故だ。 だが、気づいたら下で立ってい...
Read More「体操は身体の運動に対する正しい判断の支配であり、それによつて精神の無秩序も整へられることができる。情念の動くままにまかされようとしてゐる身体に対して適当な体操を心得てゐることは情念を支配するに肝要なことである。」 人生論ノート by 三木清 武術はまず型を通して学ぶ。 太気拳には型というものはないが、ひとつひとつの動きに原理原則がある。 原理原則・秩序のある動きを身体に覚えさせる...
Read More人生は選択の連続だ。 どのような選択をするか、そしてその判断基準はなにか。 それがその人の人格やライフスタイルを決めると言っても過言ではない。 以前の私の主な判断基準は「損か得か」「それが将来、自分のためになるかどうか」であった。 進学や就職など、人生を方向づけるような大きな選択肢であればあるほど、その傾向は強く現れていた。 ところがここ10年ほどは、何かを選ぶとき「好きか嫌いか...
Read More稽古のあと、みなさんにバースデーを祝っていただいた。 前日も水曜稽古組の方々に祝っていただいた果報者である。 私の誕生日はクリスマスなどと違ってきわめて個人的な祝い事だ。 自分ひとりでなんとなく浮かれているが、周りの人は普段と変わらぬ日々を過ごしている。 大人になって自分の誕生日を嬉しがるなんてみっともない、という感覚が、いつの頃からかある。 それが誰かに祝ってもらうことによって...
Read More